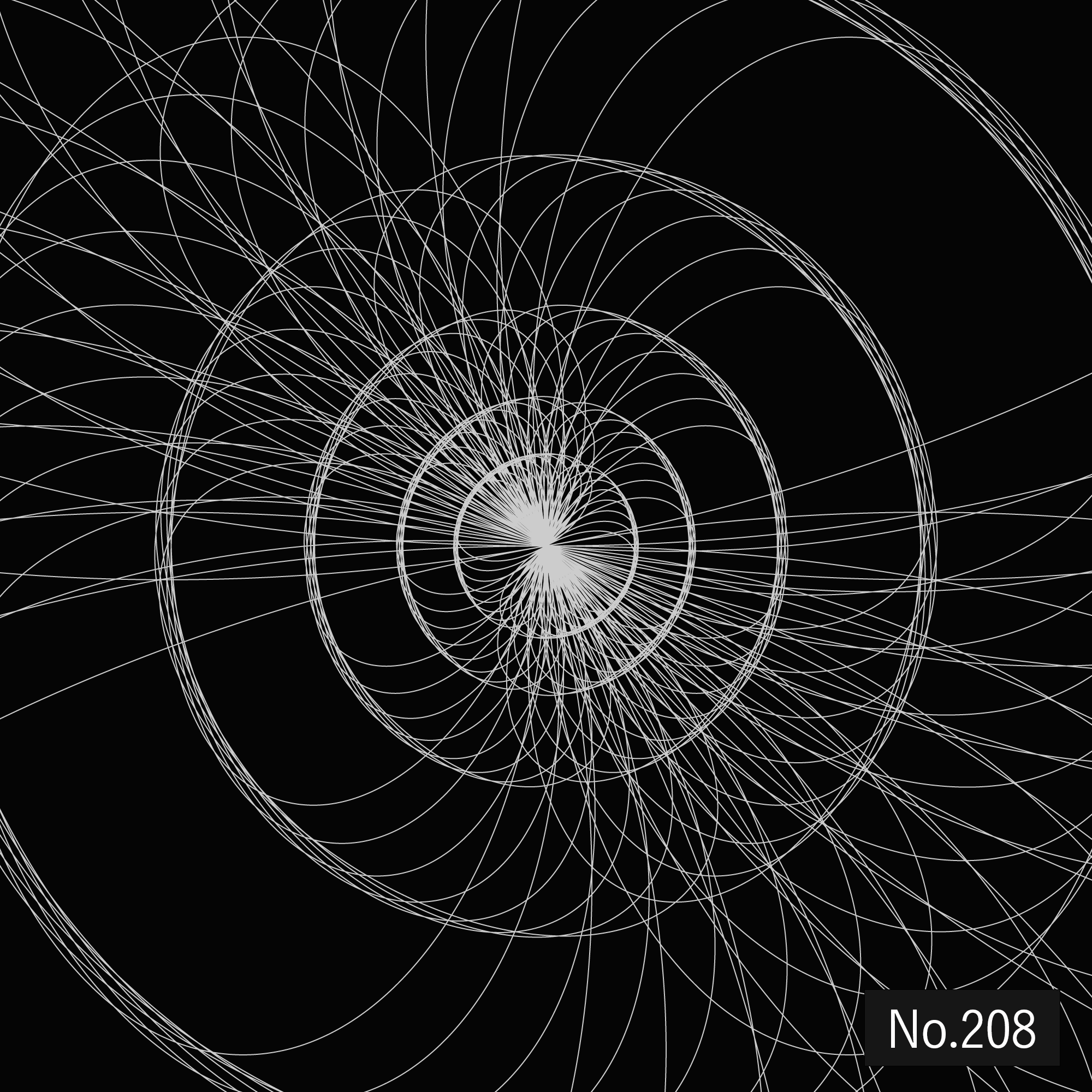
自分が大学進学に際し建築学科を志望に決めたのは、高校3年生の時に地元の本屋で見つけた「芸術新潮」の安藤忠雄特集を手に取ったのがきっかけであった。それまで一切建築家の存在など知らなかったのだが、その特集において彼が手掛けた建築群、そしてその背景となる考え方、日本文化との関係性などのテキスト等を読み、こういうアプローチがあるのだと知り、過去の自分の疑問に何か答えをくれそうな気がした。もともと父親が土木エンジニアで橋梁を専門としていたこともあり、自宅には青焼きと呼ばれる設計図の美しさであったり、構造計算のためのパンチカードと呼ばれる不思議な暗号のようなものを遊び道具にしていた自分には工学、そして巨大な土木建造物というものには妙な親近感を持っていた。そして育ったのが東急田園都市ニュータウン、そして高校生になるころには隣町に港北ニュータウンという、新しい概念の街に住まい、また別の新しい概念の街ができていくのを横目見ていた。土木やニュータウンという身近な存在に対しては、比較の対象もなかったので、それらの良し悪しや好き嫌いという感情すら発生することはなかったのだが、何かしら自分の体験してきた土木建造物の醸し出す冷たい雰囲気や、ニュータウンを生きる中で感じてきた血の気の通ってなさのような、そういった無意識の中に澱となって蓄積された負の感覚があったからこそ、建築家という存在に興味を持ったのだと思う。
その芸術新潮の本は安藤忠雄特集以外にも、中島千波さんという画家の方が子どもたちにヌードデッサンを教える記事や、中平卓馬さんというアルコール中毒になった写真家が沖縄に訪れるといった記事、あとは白装束で温泉治療する集団のルポタージュ、あとは密教の曼荼羅紹介など、自分にとって経験したことがない世界が沢山記事になっていて、今となっては自分の原点といえる一冊だったと思う。そういう周辺の世界観が、安藤忠雄さんの設計した住宅、寺院、教会、集合住宅などをより一層魅力的に感じさせる演出になっていた。また、小中高とキリスト教会と深く関係を持っていた自分にとっては、そのキリスト教会で垣間見てきた非日常とそれら雑誌内の非日常は重なるところがあり、それらの源流をたどってみたいという純粋な興味が、その後時間をかけて自分で体験する行動につながったのだと思う。そういえば安藤忠雄特集の中で、彼の20代のシベリア鉄道に乗ってヨーロッパ建築視察に行ったというお話が書いてあった。自分も何を体験してきたのか、そういったことをいつか書いてみようと思う。
その後社会人として広告代理店というまた不思議な仕事に関わることになり、そしてそれなりに大手の制作部門という競争率の高い部門に入りそれなりの視線にさらされながらクリエイティブを仕事にしていく中で見た人たち、そしてその人たちの行動は今思えば奇妙だった。20代前半当時、広告クリエイターとして認められる第一歩が、日本国内の新聞系の広告賞に入選し、そのカタログに名前が載ることだった。20代から30代のクリエイターたちは、こぞってこれら賞に応募するための創作を空き時間にこなしていた。そういった賞は、最低限世相の捉え方や、日常生活の捉え方のちょっとしたズレみたいなものが表現されていないといけなくて、クリエイターは自分が何を面白いと思っているのかみたいなことを探しつつも、日常業務の中で潜在意識に刷り込まれた広告制作のお作法、特に企画会議のノリでぽっと出てきたよくわからない変なアイデアに引っ張られてしまった、という作品が多かったように思う。特に広告というものに憧れを持たずその業界に所属していた自分にとっては、それら年鑑で見る作品群に全くいいなと思えなかった。そして今となっては広告の醸成してきた、そして消費者も楽しんでいたであろう、マス広告というひとつのクリエイティブのジャンルは消えかかっている。
その後、外資の広告代理店に所属していたときも、賞に応募するというのはクリエイティブ部門では普通のことで、特に外資系のクリエイターは海外の受賞歴を履歴書に書くことがひとつのステイタスになるため、クリエイティブ部門をあげて予算をつけたりしながら、みながこぞってそれらにチャレンジしていた。今思うと、そこまで効率化された職場ではなかったし、何をやっているのかわからない人たちがほとんどだったのでどこまで時間を割いていたのかはわからないけど、そういったクライアント向けの本業の仕事のみならず、賞のために個人的な創作をする、という姿勢にはおおいに学ぶところがあった。ただいま考えてみると、それら賞のための創作以外に、自分の世界観を深くしていくような創作を個人的にやっている人は少なかったように思う。何人か、賞には全然引っかからないけど変なアウトプットを夜な夜なしているクリエイターが何人かいて、そういう人たちは今は広告業界とかではなく、独立したり先生をしていたりする。こういった賞のためではなく、自分のために時間を割いていた人の方が、今の自分には親近感が湧く。ただ、そういったクリエイターは組織内で出世はできないのが現実だと思う。
賞のための創作と、個人的な世界観を追求する創作。どちらを選択するかは、個々のクリエイターの裁量にある。自分にとって重要なスタート地点となった、芸術新潮という本の中では、自分には無い世界が多々表現されていた。生活の中で自然と発生した風習、創作を突き詰めていく中でアルコールに溺れていく芸術家の成れの果て、鉛筆一本で眼前のフォルムを紙に落とし込むスキル、そういった本の中に登場する人や風景は、損得感情抜きにしてたどり着いた姿に思える。振り返って、私が20代から30代にかけて、賞のためにあれこれしていたクリエイターたちは、何を極めようとしていたのだろうか。
自分はそういった賞を獲ることに興味が持てず、加えてそういったお作法での表現がどこか嘘くさく感じて素直にできなかったので、ただその時に興味を持ったことに時間を費やして、学習そして経験を重ねてくることを続けてきた。その場に行ってみる、学校に行く、図書館にこもる、ひたすら作品を見に行く。そういった積み重ねの蓄積の中で、創造物の内包する普遍性を持ったパターン、相似形のようなものが脳内に浮かび上がってくる。そして自分の存在がいかにして存在しうるか、時間を巻き戻し抽象化したイメージを捏ねくり回していると、人間の身体構造と同じく、ある種の構造の中に自分が配置されていることに気づかされる。そういった気づきを内包した創造を私は続けたいし、その探究と表現の連続には終わりがない。死ぬときが終わりであろう。
高校生当時の自分自身に対して今の自分は、根本は何も解決せず変わっていないともいえるし、時間をかけて前進しているともいえる。まだまだ知らない世界も多いのだが、知らなくとも応用が効く方程式のようなものは掴んでいたりもする。自分だけの言語で創作をする、自分だけの世界観を表す、そのスタート地点にはやっとたどり着けたような気もしているが、格段に若い時に比べて選択肢が狭まっている自分の存在を感じる。さまざまな一見マイナスとも思える条件が過去の経験や知識を総動員し何かを表出していくことを促す。今は自分の中の興味を深く掘り下げるばかりでなく、表現し続けることに重点を置かなくてはならなくなってしまった。今の自分には生きること自体と、創作および表現は切り離せない。生きるために表現する、表現することで生きる。
自分はどうありたいか、を書こうと思ったが、自分はこれしかできなかった、というようなことばかり書いてしまった。結局どうありたいかとか、こうありたいと考えるよりも、興味あることへの行動履歴、やってしまった事やその時思ったことの方が、その人の本質を表しているとも思う。なので、ここに書かれていることすべてが、私自身がどうありたいかの極めて本質的な説明である。
私は自分自身を深く掘り下げ、そのまま表現したい。そして、アート、デザイン、コマーシャル、ボランタリー、すべてが同じ姿勢で表現したい。
本日のタイトル画像:
Infinite loop geometric pattern No.208
リンク: Instagram @sugitad1